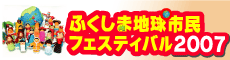このページは、現在のホームページ管理人(現在は宍戸竜司です)が話題を勝手に取り上げるコーナーです。 (^O^)
このページの記事を参考にされる方は、まずこちらの注意を必ずお読み願います。
**************************************************************
目次
2002/02/24 よろしくお願いします
2002/02/24 NHKでバングラディッシュのグラミン銀行を取り上げました
2002/03/31 海外での医療事情や傷病ついて(その1、一般的なこと)
2002/06/19 海外での医療事情や傷病ついて(その2、感染したら人命に係わる病気、狂犬病)
(だらだらやたら長くなってきたので、そのうちレイアウトを直します)m(__)m
**************************************************************
2002/02/24 よろしくお願いします
現在このホームページはIBM ホームページビルダーを利用し、WindowsのNetscape Navigator 上で表示の確認を行いながら作成しております。
WindowsのInternet Explorer上や,Machintoshの Netscape Navigator、Internet Explorerを利用してご覧の場合、行の変更部分の一部やレイアウト、文字の大きさなどにお見苦しいところがあることを確認しております。これから少しずつ改善していきますので何とぞご了承願います。
今後この「管理人の部屋」のページには、海外渡航時の安全のヒントや熱帯病の予備知識、簡単な途上国開発の話などのほかに、「おもしろおかしい」事を書いていきたいと思います。乞うご期待。
(^o^)/
2002/2/24 NHKでバングラディッシュのグラミン銀行(マイクロクレジット)について取り上げられました。(掲載場所を移動しました)
2002年2月24日(日)21時より NHK総合テレビ(再放送は現在未定です)
NHKスペシャル「世界はどこへ向かうのか〜問われるグローバル化」
現在最も注目されている社会開発の手法の一つです。
この番組の中でバングラディッシュのモハメド ユヌス(ムハマド ユヌス、ムハンマド ユヌスとも)のグラミン銀行(グラメーン銀行とも)が取り上げられました。このグラミン銀行とはいわゆる自立を目的とした小口融資(マイクロクレジット)を行っている銀行です。これは途上国の人達に対し単なる援助という形ではなく、直接の小口融資を行うというものです。
バングラディッシュでは極貧生活をする多数の人達の暮らしをこの銀行が大きく変貌させました。この銀行は銀行業務の定石に逆らって設立させたもので、貧者の中でも特に貧しい人々にのみお金を貸し付けます。例えば農具、雌牛、ミシン等を購入する資金として数ドルを貸し付けます。(ほとんどが無利子)「貧困の解消には貧しい人々が資産を作り出していく以外に道はない」(ユヌス談)との考えに基づいています。
ユヌスがバングラディッシュで出会った婦人は竹製の椅子を作っていたましたが、お金を前借りした仲買人に品物を売らなければならないために一日に2セントしか稼げませんでした。この婦人に対しわずか4ドルの運転資金を貸し付けることにより、その利益は一日2セントから1ドル25セントへ増大し、返済後は利益をさらに伸ばしていったと云う例があります。このように小口資金を字の読めない人や担保を提供できない人に対し行いました。
現在世界80カ国以上にこの小口融資が行われるようになっています。
このマイクロクレジット(小口融資)を貧しい人に直接行うという自立を目的とした途上国の開発は、もっとも注目されている開発の一つの手法として現在大きな関心を持たれています。また運営はNGOが銀行業務を行い、国や援助国や国連等の国際援助機関が資金を提供するという形でも行われています。現在注目されている開発の手法として、NHKの再放送をご覧になることをお勧めいたします。(ただし最初の30分くらいはアルゼンチンの経済問題について取り上げられています。この問題とグラミン銀行を一緒に取り上げられた事には少し疑問を感じましたが・・・・)なおユヌス博士はノーベル平和賞有力候補との話。
参考になる文献
ムハマド・ユヌス自伝 貧困なき世界をめざす銀行家 ムハマド・ユヌス著 早川書房 2,000円
AERA 1993年4月20日号 Vol.6
No.16 P26-28
毎日新聞 平成13年8月17日(金) P12,13
グラミン銀行総裁のムハマド・ユヌスが、雑誌アエラの最新号(2002 3/25 号 3月18日発売)の表紙になりました。
2002/03/31 海外での医療事情や傷病について(その1、一般的なこと)
「国際交流/協力」と云うことで、海外に渡航して直接活動される方も多いと思います。そんな時に特に心配なのは海外での医療事情や防犯などでしょうか。と云うわけで、今回から海外渡航時に参考になる(かなあ)と思われる事について、「つれずれなるまま」に書いていきたいと思います。
これらは私が前に作成した資料から、皆さんに関連するようなことを、あっちゃこっちゃから抜き書きしています。 しかし元々の資料は途上国で長期間活動する人を想定して作成していますので、対処法等について極端なものもあり、どうしても短期間の渡航や欧米諸国等の先進国への渡航には当てはまらないこともあると思います。しかし過度な心配をする必要は全くありません。 あくまでも参考にしていただければ幸いです。また”日本語”の文体が変なところもあると思いますが、この辺は笑って大目に許してやってください。
(^^ゞ ポリポリ
さてさて、今回は一般的な海外の医療事情とその注意について取り上げたいと思います。
◎ 大原則 ― 自分のことは自分で守る!
日本でも海外でも自分のことは自分で管理する。どこに住んでも基本です。「疲れた」と思ったら休むこと!(療養は身体を休め治療に専念することが目的です) 「健康管理」の考え方は日本にいるときとは全く異なっていることを理解してください。
◎ でも、ある程度事前に「事故に遭ったら」「病気になったら」を想定しておく
どんなに注意していても事故に遭ったり、病気になったりする事があります。と云うわけで、ある程度想定してください。(持っていく薬、簡単な会話帳の準備、海外旅行者保険の購入、緊急連絡先をメモしておく、大使館や領事館などの在外公館の場所の確認等)
持病のための薬は現地では調達ができないと思って、すべて持参することを勧めます。また風邪やビタミン剤等の一般薬は粉末や顆粒タイプではなく、錠剤タイプを勧めます。粉末や顆粒タイプの経口薬は特に途上国では一般的ではありません。空港のセキュリティチェックで粉末である場合に麻薬やドラッグ類と、いらぬ疑いを掛けられることがあります。もちろんそうではなくても、成分について延々と説明を求められることもあります。一般薬の包装箱の中には英語の表記があるものもありますので、その場合は箱のまま持っていくことも好いでしょう。
日本の健康保険は利きませんので病院にお世話になった場合は全額自己負担になることが普通です。(その反対にすべての医療に係わる経費は国が負担すると云うところもあります)
重大な事故や病気になり、滞在している国で対応ができない場合は、日本へ又は途上国の場合は近くの先進国へ緊急移送する事になる場合があります。その場合にはものすごい金がかかります。特に旅行代理店によるツアーではない、個人旅行の場合は全額自己負担になります。(チャーター機の場合、西アフリカからヨーロッパへの移送には約700万円から。日本へは数千万円かかる事になります。それほど緊急を要する必要がなく、緊急移送会社が定期便を利用すると判断した場合でも数百万円かかります。また緊急移送と云っても患者以外の付き添う家族や友人の移動分は通常カバーしません)
と云うわけで、旅行前には海外旅行保険に入る事を勧めます。これは医療機関に世話になった場合に経費を負担してくれるほかに、このような緊急移送にも対応する特約もありますので購入時に確認して、また利用法については誤解のないようにしてください。(緊急移送に保険が対応していると云っても、現地の医療機関と緊急移送会社との間でその必要性が話し合われた上で決定されます。したがって被保険者側が緊急移送会社を通さずに勝手に移送を依頼した場合は、全額自己負担になり、事後に請求しても支払われません。保険の内容を十分に確認してください)
事故は思わぬ時に遭遇します。観光地のグアムでは溺れる、海流に流されるなどの水の事故により、年に数人の邦人が不幸にも亡くなっています。
◎ 医者にかかったら信用するしかない
現地でかかった病気には現地の医者、薬、治療法が1番です。現地の医者を信頼して下さい。(と云うか信頼するしかない)緊急時においてもまずは現地の医療機関にお世話にならざるおえません。
熱帯感染症の場合は特に現地の医者が頼りになります。現地の医者なら例えば、定期的な発熱があり、症状を見ることによって即座に「マラリア」だと疑うことができます。日本の開業医で、まず「マラリア」だと判断できる医者はいないでしょう。
信用せよ、と云っても、注射時に消毒もしなかったり、針を使い回しするような医者は避けてください。(この辺は見極めが大事)また重大な医療事故を防ぐためにも十分に話し合ってください。
◎ 日本と外国では対処も対応も違う場合がある
海外において日本の医師と多少治療法が異なることがありますが、それは欧米と日本のやり方の違いや、習慣の違いです。具体例を上げてみますと・・・・。
1) 注射の刺し方
筋肉注射をする場合日本では3本の指でつまむように持ち、「痛くないです、すぐ終わるよ。ほーら痛くない痛くない」などと云いながら斜めの角度でゆっくり刺します。(そもそも痛くない注射があろうか!)
一方しばしば外国人医師は、握りこぶしのようにして注射器を握り(逆手!)、時に「このチューシャ、たいへんたいへんイタいです、でもワタシはすぐにおわるようにドリョクします、アナタのために」(ちょっと英語の言い回し風?に書いてみました)などと、はっきり云いながら一気に針の根本まで垂直に刺し、持ち替えて注入します。これは欧米式の注射法です。(この逆手持ちは最初ヒジョーにビックリしますが、「必殺仕置き人」に殺られる気分が味わえます。チャララー)
2) 発熱時の処置
日本では暖かくして休み、入浴はひかえ、冷やすのは頭部のみの場合が多いと思います。ところが現地医者からでは冷水シャワーを指示される場合があります。熱射病等、緊急に熱を下げる必要のある場合は背中に氷を敷いて休むように指示されることもあります。これも欧米式と日本式の違いです。日本で赤ちゃんが急に発熱して病院にくる場合、おばあちゃんが心配して服を多く着せ過ぎたことが原因、ということが多々あります。その場合、はだかにするとたちまち熱が下がることが良くあります。特に、熱帯、亜熱帯地方のような高温地域では、身体を冷やすことは効果があります。
3) 海外の医者は滅多に「抗生物質」を出しません
日本のように「抗生物質」を出しまくる国はありません。(海外では風邪ぐらいではまず出しません) 抗生物質は本当に必要な時に使用しないと耐性の体質になり、いざというときに全く効かなくなります。 そもそも抗生物質は「細菌」に対して効く薬なので、ウイルス性の病気には効きません。
まだまだたくさんありますが、要するに日本と海外の医者は違うと云うことを理解していただければ、あなたもわたしも安心。
◎ 日本と海外は生活環境が異なっている
最近医療事情が飛躍的に良くなり、ある意味では「無菌的環境」となった日本人と、途上国の様に厳しい環境を生き抜いてきた現地の人とは体の抵抗力が根本的に違います。
例えば現在日本の小学生で、蟯虫や回虫など腸管内寄生虫をもつ子どもはほとんどいません。(と云いながら最近有機野菜ブームの生野菜を、ろくろく洗わないで食べることにより、寄生虫が増えてきたとの話) また現在多くの日本の高年の方がすでに持っているA型肝炎の抗体は、衛生事情の改善により現代の若者のほとんどはワクチンの注射による接種でしか持つことができません。
このような理由で、いくら現地の人と同じ生活をしようと思っても根本的に無理があります。
いわゆる「旅行者下痢症」も、現地の人が食べて平気な場合でも、抵抗性がない日本人が食べると当たる場合もあります。生の魚貝類を食べる習慣がない国で、サシミや寿司を食べて食中毒による下痢になった場合は、そもそも衛生に関する認識が根本的に異なる場合から起因しています(ほとんどが腸炎ビブリオによる食中毒)
抵抗力は時間と共に付いていくにしても、短期間の滞在では絶対に無理しないようにした方が無難です。
◎日本と同じ対処は期待するな
途上国では薬や治療器具が不足していることは当たり前です。また交通手段がないこともしかり。重大な事故や病気になっても、日本人だからと特別な対応を期待しても無い物は無いのだから仕方ありません。 日本のように電話一本で救急車が来ることは期待しないでください。
先進国での受診でも言葉の違いから正確に症状について説明できずに、正しい処置ができない場合も考えられます。
今回のまとめ
◎大原則 ― 自分のことは自分で守る!
◎でも、ある程度事前に「事故に遭ったら」「病気になったら」を想定しておく
◎医者にかかったら信用するしかない
◎日本と外国では対処も対応も違う場合がある
◎日本と海外は環境が異なっている
◎日本と同じ対処は期待するな
次回からは具体的な病気(主に感染症)について取り上げたいと思います。
閑話休題 ―――― ちょっと一休み (^O^)
海外に納豆をお土産に持っていくときは、どんなに美味くても「わらづと」入りは止めましょう。入国時に「わら」が植物検疫で止められるのはもちろんですが、スーツケース内を検査を受けて見つかって、「わら」を開いたときに腐った豆が出てくるわけですから、納豆なんて知らない人は非常にビックリします。ましてこれを食べるなんては想像もつかないでしょう。「おまえこれは腐ってるぞ。処分してやるから、ここに棄てていけ、棄てていけ」と、本当に親切心から云ってくれる検疫官がいて、ごっそり棄てられた、なーんて話があります。(腐った豆を食べ物だと検疫官に説明できれば好いのですが…・できます? こりゃ、ウントムズガシベナア)
とまあ、こんな感じでやっていきたいと思います。次回は「医療事情」の2回目ではなく、他のトピックかも・・・・。お楽しみに!
(^_^)/ ̄
2002/06/19 海外での医療事情や傷病について(その2、感染したら人命に係わる病気、狂犬病)![]()
前回からずいぶん時間が経ちました。今回から特に注意しなくてはならない感染症を取り上げます。人命に係わる感染症から、それも危険度が高いものから取り上げていきます(順番はワタクシメが勝手に危険だ!と思うものから取り上げていきます。ですので、蟯虫やサナダムシなんて、そうすぐに人命に係わらないものはずーっと後にして、発病したらすぐに死ぬ恐れがあるもの、誰でも感染する可能性があるもの、速やかなる対応が必要なのもの等を勝手に考慮して取り上げます。あしからず)さて、第一回目は狂犬病です。
狂犬病 ― 発病したら必ず死にます (注意度A)
◎狂犬病は英語でラビエス(Rabies)と云い「人獣共通感染症」です。ただし感染するのは哺乳類だけですが、決して犬だけの病気ではありませんので注意!理屈では鯨でもコウモリでも感染することは可能ですし、実際コウモリから人が感染したと云う報告があります。
年間5万人が死亡していると云われ、途上国でも先進国でも感染例はあります。(現在狂犬病がないのは日本(1956年撲滅),イギリス,スカンジナビア半島,オーストラリア,ニュージーランドだけ) 狂犬病は決して過去の病気ではありません。
狂犬病はたまたま噛まれることにより唾液中のウイルスが侵入し感染する病気で、とにかく一番恐ろしいのは「いったん発病すればまず治癒することはない」と云うことです。注(1)
つまり100%死ぬと云うことです。(本当かどうか、過去に一人だけ助かった人がいるらしいのですが)
◎欧米等先進国での感染
キツネ(Fox)、アライグマ(Raccoon)、コウモリ(Bat)等、アメリカではさらにスカンク(Skunk)等の野生動物が狂犬病ウイルスを保有していると考えられ、噛まれるなどして直接伝播(感染)するか、野生動物から犬、ネコ等の家畜を介してヒトに伝播します。コウモリが生息する洞窟では、直接噛まれることのほかに、洞窟内を飛び回るコウモリの唾液が霧状に漂っていて、それを吸い込むことで感染することも起こり得ます。
◎途上国での感染
ほとんどが犬に噛まれることから感染。特に野犬の取り締まりができていない都市部では注意。飼い犬でも日本のように狂犬病の予防注射をしている犬はほとんどいません。(調査によると、タイの都市部でウロチョロしている野良犬の約50%がウイルスに感染していると報告されています)注(2)
◎日本での感染例
日本では飼い犬の登録、ワクチンの接種、野犬の取り締まりなどにより狂犬病の制圧が成功している。(ハワイ、イギリス同様、島であることが成功の元のようです) 日本では1958年以来発生していないが、1971年にネパールで感染し(噛まれた)日本に帰国後に発病した例がある。注(3)
◎人から人への感染
ヒトが誰かに噛みついて他人や動物に伝播させると云うことはあまりありませんので、ヒトは狂犬病の最終宿主、つまり「伝播の終点」とも考えられますが、医原的に伝播する事も考えられます。(例として、感染患者から取り出した角膜等の臓器移植などですが、これは狂犬病だけに限ったことではありません)注(3)
◎感染する(噛まれる)とどうなるか/狂犬病の特徴
狂犬病に限りませんが、感染した場合、病気が発症するまでを「潜伏期間」と云います。(感染してすぐに発病するのではありません) 狂犬病の特徴は噛まれて(感染して)からの潜伏期間がまちまちな事で、短くて2週間ほど、一番長くて7年という期間で発病し、平均は感染してから1−3カ月で発病します。(前記したタイの都市部の野良犬は、要するに感染はしているが発病してない犬と云う事になります。しかし発病していない犬でも感染していればウイルスを伝播させることができます)
では発症するとどうなるのでしょう?ワタクシメが実際に某国の野原で見た犬の場合は、まるで酔っぱらった様にふらふらとうろつき、バランスを崩して倒れると足をバタバタさせて「ワワワワワワワーン」と啼き叫んでいました。(狂犬そのもの) ヒトの場合はビデオで見ましたが、・・・・悲惨でとてもここには書けません!最後は麻痺し死亡します。
狂犬病のもう一つの大きな特徴は、前記したように潜伏期が長いために噛まれてからも治療できると云うことです。つまり「狂犬病は感染を受けてからのワクチン接種によって予防し得る」
のです。注(4) (もちろん噛まれてから一ヶ月後のワクチン接種では遅いのですが)
◎狂犬病を発症している犬の特徴(ネコや家畜、野生動物も同様)
◆行動が奇妙である(突然静かになる、落ち着かない、怒り出す)
◆口から泡を吹いている、餌を喰われない、水を飲めない
◆時々狂ったように走り回り、ところ構わず物や人を噛みまくる
◆上のような症状の犬が一週間以内に死ぬ
(ただし上の特徴は発病している場合で、単に感染し発病していない場合には、普通と全く変わらない行動を示します)
◎狂犬病を防ぐには
◆とにかく噛まれないこと
途上国では絶対に野良犬に近づいてはだめです。人なつっこい野生の動物(リスなどの小動物)もいますが手は絶対に出さないでください。いきなり噛んで逃げることがあります。飼い犬でもその辺をウロチョロしている野良犬との接触があれば、感染しているとも考えられます。
◆狂犬病の多発地帯に長期で行く場合は
曝露前接種、つまり旅行の前にワクチンを接種することを勧めます。理想としては旅行前に3回接種しますが(4週間隔で2回,さらに6〜12ヵ月後に1回皮下接種して基礎免疫をつける)、時間がないときや、短期の旅行の場合でも、せめて1回だけでも接種しておくと好いですね。
日本製の狂犬病ワクチンは玉子を利用していますので、玉子アレルギーの人は注意。また日本製でも接種するとかなり「きます」。(ワタクシメが接種した各種ワクチンの中では一番グッタリしました。午前に接種して午后はへたっていましたんで・・・・)さらに1回7千円位して結構高いです。
なお日本国内での詳しい接種方法や場所は大きな病院や保健所等に問い合わせ、医師等と必ず相談し確認してください。
◆もし噛まれたら必ず狂犬病感染への対応を考える
途上国で犬や野生動物に噛まれたら必ず狂犬病感染への対応をとってください。特に東南アジア諸国で野良犬に噛まれたら「感染した!」と考えて対応する方が無難です。
まず噛まれたら、知人やホテルの従業員や、警察の誰でも好いので犬に噛まれたことを訴えて、病院につれていってもらいそこの医師と相談することを勧めます。(もしワクチンの接種が必要と判断される場合は、曝露後接種、つまり噛まれた後、第一回目の接種を72時間以内(3日以内)に行うことになります)
ただし現地でのワクチン接種には十分に注意してください。(途上国のワクチンはマウスを使う旧型のため、頻回接種により重篤なアレルギー性脳炎(後麻痺)を誘発する事があります。注(5)
十分に医師と話し合ってください。可能ならば日本の医師にも相談することもお勧めします)
また当然ですが、噛まれた後もしっかり消毒するなど外科的な治療もしてもらいましょう。そもそも狂犬病でなくても動物の口中は汚いものです。
時に「噛んだ犬を捕まえてこい。狂犬病か調べるから」と云われることがあるかもしれませんが、実際のところ捕まえるのは困難です。
今回のまとめ ー 狂犬病
◎犬だけではなく、人も感染/発病する病気
◎発病すれば必ず死亡するが潜伏期が長いために感染後(噛まれた後)のワクチン接種でも有効と云う特徴がある
◎なにはともあれ、噛まれない様にする。むやみに動物に近づかない触らない構わない(一番有効な予防法です)
◎不幸にも途上国(特に東南アジア)の野良犬に噛まれたら狂犬病対策を必ず考える
◎予防接種や噛まれた時には、まず医師に相談
◎現地のワクチンは副作用の恐れも「無きにしも非ず」なのであまり勧められません (でも狂犬に噛まれて現地のワクチンしか無い場合は・・・・選択は本人次第です。要するに犬に噛まれないようにするのが一番大事なのです!)
私は犬に噛まれました! I was bitten by a dog!(アイワズ ビーテン バイア ドッグ!)
私は狂犬病が心配です。 I am worried Rabies. (アイアム ワーリード ラビエス)
私は狂犬病の予防注射をこの国に来る前にしました。 I had an antirabies serum injection before I came
to this country.
狂犬病(名詞) rabies、canine madness、hydrophobia、lyssa、mad dog disease
注(1) 竹田等 p.250から引用
注(2) 長崎大学熱帯医学研修講義ノートより
注(3) 竹田等 p.249から参考
注(4) 竹田等 p.250から引用
注(5) 竹田等 p.250とPromedica「狂犬病ワクチン」の項目を参考
参考文献;
竹田美文等 新熱帯感染症学、南山堂、1996
メジカルビュー社 ステッドマン医学大辞典 CD-ROM版、1997
南山堂、 Promedica 医学大辞典 CD-ROM版、1998
Werner D. Where there is no doctor, Revised ed. Macmillan, London,
1993
最近よく聞く「狂牛病」は発生原因が「狂犬病」とは全く異なります。(^_^;)
閑話休題
狂犬病と云えば・・・・・。
町の狂犬病集団接種で家の犬を役場につれて行った時のことです。ずうたいがでかいのに注射の恐怖でガタガタ震え腰を抜かしている犬や、ケンカを売りまくる犬など役場の駐車場は大騒動。で、まずは犬に注射をしてもらい料金を払う受付へ。役場の職員さんが「あー、犬に変わりはありませんか?」、なんと!なんと心優しいではありませんか!「はい、いたって元気です。ありがとうございます」と答え料金を払い登録を確認し家に帰ったのです。しかし、なんで犬の容態なんて聞くんだろう?なんでだろう、なんでだろう、犬に変わりはありませんか?犬に変わりはありませんか?・・・・・・・・で、気が付き一人で大爆笑をしてしまいました。要するに犬の容態を聞いたのではなくて、昨年登録した犬と変わってないかと云うことを聞いたのです。逃げたり死んだりして、昨年の注謝時と犬が変わっている事は十分にあり得る事なんですよねー。おまけに家の犬は、ワタクシメの物心付いたときにすでにいた犬から何代か変わりましたが、名前はずーっと同じなのです。(ヘタすると役場の登録では家の犬が30年以上生きていることになってるのではないだろーなあ?)馬鹿な話でスミマセン。
そろそろ犬のフィラリア予防薬の開始時期ですなあ。
**************************************************************
この「管理人の部屋」の記事に関してのメッセージは、記載者の宍戸(HP管理人)![]() fugnet@@mail.goo.ne.jp まで。(@マークはひとつです)
fugnet@@mail.goo.ne.jp まで。(@マークはひとつです)
(注意)
[免責事項について]
1,この「管理人の部屋」の記事に関しては、すべて記載者の責任において取り上げられています。従って"国際交流・協力団体「ふくしま地球市民ネットワーク」(ふぐネット)"は一切の責任を持ちません。また"国際交流・協力団体「ふくしま地球市民ネットワーク」(ふぐネット)"は、このページ「管理人の部屋」に関する一切の問い合わせや質問に関してもお答えできません。
2,この「管理人の部屋」の記事を参考する事によって、万が一盗難を含む金銭的障害、精神的障害、傷病を含む身体的損害、その他の障害、トラブル、事故などが発生しても、記載者は一切の責任を負いません。利用者は利用者個人の責任において参考にして頂くことをあらかじめご承知おき願います。
3,この「管理人の部屋」の記事に関して、記載者あてに出されましたメッセージに対しては、必ずしも回答を保証するものではありません。
2002年2月12日 「管理人の部屋」記載者